おはようございます。Satoshiこと、Yamamoto.satoshiです。
本日は前回に続きNHKからのテーマを届けます。
親になるってどうゆうこと?それは脳科学の視点から考えると、「親性脳(おやせいのう)」が育児を通じて育まれることだそうです。「親性脳」とは、子育てを適切に行うために必要な脳や心の働きを指すそうです。「親性脳」は、子どもとかかわる時間と経験を経て育まれるもので、性別に差はないようです。
人は、かつては集団生活の中で子育てを行ってきました。現在の日本は核家族化し、人の手を借りながら集団生活の中で子育てを行うことができない社会構造となり、夫婦で子育てを行う人が増えているのが現状です。
つまりは、共同養育=母親が所属する集団で協力しながら子育てを行うことで、子どもの生存率を高めてきた社会構造が崩れ、子育てする環境が大きく変化しました。しかし、集団=共同養育の場が、無くなったわけではありません。子ども・地域・親をつなぐ場が、行政や保育園が現在は担っている面が大きくなってきました。
「親性脳」は、こうした共同養育の場でも養われていくもので、個人差はあるもののゆっくりと養われるものです。自治体の「産後ケア」や保育園のコミュニティーから広がっているのが現在の日本の構造のようです。
「親性脳」は、子育てを行う時間と経験を徐々に経ながら、共同養育の場で養われることを意識して、子育てを見てみる視点も大切かもしれません。焦らず、ゆっくりと子育てと向き合ってみたいと私は思います。

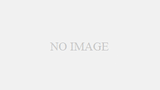
コメント